立命館とVenture Café Tokyoが毎月1回、立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)で開催しているイノベーション促進プログラムOIC CONNÉCTは、「イノベーションは社会とつながるキャンパスから」をコンセプトに、新しい挑戦をしたくなるような機会を提供し、イノベーション・コミュニティを創出することを目指しています。OIC CONNÉCT、そしてVenture Café が大切にするミッションは“Connecting Innovators to Make Things Happen.” OIC CONNÉCTで生まれた新たなできごと“HAPPEN”を参加者や関係者へのインタビューからご紹介します!
第7回となる今回は、鰹節や昆布・煮干しなどの出汁素材を取り扱うヤマキウ株式会社の鈴木 彰さんと衣食住遊、様々なカテゴリのヴィーガンコンテンツの開発・導入の伴走などを行う合同会社KYOTOVEGANの玉木 千佐代さんにお話を伺いました。
イベント参加をきっかけに何が生まれたのか、お二人の想いとともに深堀りしていきます。
きっかけは、玉木さんと大豆出汁プロジェクト
2024年7月。OIC CONNÉCT初の一夜貸し切りイベント「食のミライカンファレンス(OIC CONNÉCT#23)」が開催されました。鈴木さんは主催と4つ目のセッションの登壇者、玉木さんは1つ目のセッションの登壇者として会場におり、共通の知人であったOIC CONNÉCTアンバサダーのSさんからの紹介で、お二人は出会うことになります。

玉木さんは現在、創業125年を誇る和菓子の素材を取り扱う株式会社美濃与と共同で、大豆から出汁をつくる「大豆出汁プロジェクト」に取り組んでいます。
「大豆の煎り具合が濃いと黄な粉に。浅いと青臭さが残る。煎り具合が非常に難しいという壁を何とか乗り越え、3年近くかけて商品化に至った。」と玉木さんは話します。
何とか商品化に至った大豆出汁プロジェクトですが、まだ大きな課題が残っていたようです。
OICでの偶然の出会いが、共同開発へ

3年という月日をかけ、商品化を実現した玉木さんたちですが、玉木さんも美濃与の方々も、本業とは異なる「出汁」のことは全くわからない状態でした。販売についても知識がない。そして何より「自分は美味しいと思うが、これは “出汁として” 美味しいと言えるのか。商品になるのか。」の判断ができなかったと玉木さんは話します。
そんな折、「食の未来カンファレンス」への登壇依頼が玉木さんのもとに届いたそうです。登壇者一覧には鈴木さんの名前が。「『出汁や…!』と思った。」と玉木さんは語ります。
そしてイベント終了後、すぐに玉木さんから鈴木さんに「一度味見してくれないか」とお願いにあがったことがきっかけで、出汁の専門家として鈴木さんがプロジェクトに参画。共同開発がスタートすることになります。

「出汁にも実はたくさん種類があるんです。弊社の強みは多くの出汁素材を取り扱っていること。何をどのようにブレンドしていくと大豆出汁に合うのかを試そうと、素材をいくつか持って行って、開発チームの方々と一緒に試作・試飲会を実施したんですが、私にとっても新たな発見があり、楽しかったのを覚えています。」と鈴木さんは語ります。
違う立場・視点の人間がいるからこそOIC CONNÉCTに行く価値がある
偶然の出会いから、共同開発というHAPPENを生み出したお二人。そんなお二人にOIC CONNÉCTに参加してみて良かったことを尋ねてみました。

玉木さん:
なかなか学生の方とお会いすることが少ないので、まずはとても新鮮でした。こういう食のミライの話はやはり、特にこの先の未来を担う若者にこそ聞いてほしいと思っています。それとOIC CONNÉCTに足を運ぶ方ってやっぱり好奇心旺盛な方だと思うんです。だからこの場で出会い、その出会いから繋がるお話というのは本当にワクワク感を非常に感じるものばかりでした。今回の共同開発もそうです。鈴木さんが入ってくれたことで、出汁をつくるにあたって視野がかなり広がりました。
鈴木さん:
今回私は玉木さんとお会いし、玉木さんを通じて美濃与さんと繋がり、結果として共同開発に至りました。違った立場や視点の方々と一緒にやるわけですから、取り組んでいく中で「こういう世界もあるんだ」という新しい発見に繋がります。出汁屋と和菓子屋が出会う。ましてや共同開発する。そのきっかけをつくることができる場所ってそうそうないんじゃないでしょうか?今やITから製造業まで色々なコミュニティがありますが、食分野ってなかなか繋がる場がなかったんです。OIC CONNÉCTは幅広い分野を扱っておられるので、食産業の横のつながりを増やしたかった私にとって、こういった場はありがたかったです。
HAPPENからビジネスの未来へ
最後に、お二人に今後の展望をお聞きしました。
玉木さん:
やはりネイチャーポジティブ(自然再興)* ですね。中小企業や個人に対して、「未来に向かって自然を大切にしていくことの大切さ」をお伝えするのが私の仕事だと思っています。私の野望は「KYOTOGRAPHIE(京都国際写真祭)のKYOTOVEGAN版をする」ことです。VEGANというワードで、世界中の方が京都に来て、一つの文化を守る。地球の未来のために何をしていくかを考える。そういう場所をつくりたいです。
*ネイチャーポジティブ=自然再興。2023年までに生物多様性の損失を止め、反転させ、2050年までに完全な回復を達成するという世界的な目標
鈴木さん:
まずは何と言っても大豆出汁の認知度を広げることです。大豆出汁は、古くは精進料理で使われてきましたが、一般的な認知度はまだ高くないと思います。日本の出汁の新しい在り方として、国内外問わず幅広い方に楽しんでいただけるような商品にしていきたいです。また、食産業はもちろん、それ以外の業界の方とも横のつながりをドンドン作っていきたいです。OIC CONNÉCTには起業家、大学教授、投資家、行政、地域の方など様々な方がいらっしゃるので、まさにうってつけの場所です。今後ともご一緒できたらと思っています!

今後の大豆出汁プロジェクト、そしてお二人の動きにも目が離せません。
鈴木さん、玉木さん、ありがとうございました!
PROFILE

鈴木 彰 Akira Suzuki
ヤマキウ 株式会社 8代目アトツギ / 食の未来 代表
1892年に大阪で創業した、鰹節や昆布など出汁素材を取り扱う会社のアトツギ。
明治大学商学部を卒業後、東京にて商社、デジマ・イベント運営の会社を経て2023年7月より家業にジョイン。近年の人口爆発や環境問題、雇用問題、戦争などによる食料調達の困難さを実際に目の当たりにするようになり、「将来私達の子孫は健やかで楽しい食生活を送れるのか?」と疑問を覚える。一方で食業界の横で繋がる機会の少なさに課題を感じ、食の未来プロジェクトを発足。エコシステムの構築によってフードイシューの解決スピード底上げを目指す。

玉木 千佐代 Chisayo Tamaki
合同会社KYOTOVEGAN 代表
バンダイで約20年間、企画・マーケティングに携わった後、2020年にKYOTOVEGANを起業。生物多様性とネイチャーポジティブを大切にし、ライフスタイルの選択肢を広げる活動を行っています。ヴィーガンは単なる食のスタイルではなく、環境や社会との関わりを意識する暮らしのひとつ。企業向けにヴィーガン対応メニュー開発やサステナブルな取り組みを提案し、京都エリアを中心に「ヴィーガンマップ」制作も手がけています。日々の選択が未来をつくる。KYOTOVEGANとともに、自分らしい選択を考えてみませんか?
OIC CONNÉCT HAPPENチーム

平田 康介 Kosuke Hirata(#HAPPENチーム最高!)
立命館大学経営学部4年生。OIC CONNÉCT 学生チーフアンバサダー。
介護現場での勤務経験がある父、そして胃ろうを経験した祖父の存在をきっかけに、介護施設の食事摂取量管理の課題を解決するサービス「めしパシャ」の立ち上げに取り組む。令和6年7月に代表の太田とともにドリギー株式会社を共同創業。

吉田 航大 Kota Yoshida(#最後のインタビュー )
4月から新社会人スタート(元立命館大学 経営学部)
チェーンの飲食店業界での就職で、全国展開を目指す集団の歯車となる。学生生活で得たノウハウを会社で発揮する予定。

玉井 芳果 Honoka Tamai(#大学生デビュー)
この4月から立命館大学経営学部国際経営学科に入学した大学一回生。OICコネクトアンバサダー。学業と両立してバイトも課外活動も頑張ります!
OIC CONNÉCTの雰囲気を知りたい方はInstagramをご覧ください!
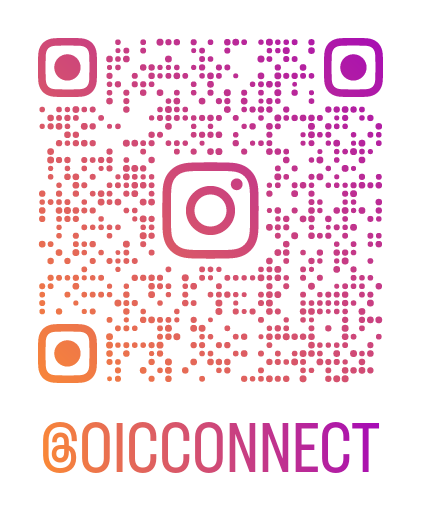
OIC CONNÉCT

OIC CONNÉCTは、学校法人立命館が主催し、Venture Café Tokyoが立命館大学大阪いばらきキャンパス(OIC)で毎月1回開催する、誰もが無料で参加可能なイノベーション促進プログラムです。
これまでOICが培ってきた「地域に開かれたキャンパス」の特徴をさらに進化させ、大学の枠を超えた「ヒト・コト・モノがより触発しあうキャンパス」を目指す取り組みの一貫として開催していきます。
このプログラムは毎月開催することで、起業家や研究者、学生など多様な人が交流し、学び合う機会の提供を通じ、関西を中心としたイノベーション・コミュニティを創出することを目指します。多様なイノベーター達による講演やイノベーションを加速させるワークショップ等を通じて参加者は学びを得ながら、そこで得た共体験を梃子にネットワークを拡げることが出来ます。








